先日、NYのコーヒー店での体験や愛されるお客さんになる方法についてお話ししましたが、今回はその根っこにある文化の違いについてもう少し掘り下げてみたいと思います。

なぜ、私がニューヨークのコーヒー店で深いつながりを築けたのか?なぜ、相手への関心を素直に表現することで「特別な存在」になれたのか?
実は、その答えは「ハイコンテクスト文化」と「ローコンテクスト文化」の違いにありました。
「察してよ」vs「言葉で教えて」
これは人類学者のエドワード・T・ホールさんが提唱した考え方で、コミュニケーションのスタイルの違いを表しています。
ハイコンテクスト文化(日本):
- 言葉にしていない「空気」や「行間」から多くのことを読み取る
- 「察する」ことや身振り手振りが大切
- はっきり言わずに、やんわりと表現することが多い
ローコンテクスト文化(アメリカ・欧米):
- 言葉でちゃんと表現されたことが一番大事
- ストレートで具体的に話すことを大切にする
- あいまいなのは苦手で、はっきりした意思表示を好む
実は、私がコーヒー店で体験した「特別な関係」は、この文化の違いを理解して、アメリカ流のストレートなコミュニケーションを試してみた結果だったのです。
なぜ違いが生まれたのか?
では、なぜ、このようなコミュニケーションスタイルの「違い」が生まれたのでしょうか?
日本が「察する文化」になった理由: 島国という地理的特徴もあり、長期間にわたって比較的均質な社会を維持してきました。共通の価値観、慣習、歴史的背景を持つ人々が密接に関わり合う中で、「言わずとも理解し合える」関係性が重視されるようになったのです。集団の調和を保つことが何よりも大切とされ、直接的な対立を避けながら相手の意図を察知することが、高度な社交スキルとして発達しました。このため、日本では「空気を読む」ことや「おもてなしの心」など、言葉にされない部分を大切にする文化が根付いています。また、長期的な人間関係を前提とした社会では、一時的な摩擦を避けることで、継続的な信頼関係を築くことができるという利点もありました。
ㅤ
アメリカ・欧米が「はっきり言う文化」になった理由: 多様な文化的背景を持つ移民によって形成された社会では、共通の文脈や前提知識を期待することができません。異なる価値観、宗教、習慣を持つ人々が効率的に意思疎通を図るためには、明確で直接的な表現が不可欠でした。個人主義的な価値観の中で、自分の考えや意見を明確に主張することが、自立した大人としての責任とみなされています。ビジネスの場面では特に、時間効率と結果を重視するため、曖昧な表現よりも具体的で測定可能な言葉が好まれます。また、法的な観点からも、契約や合意において明確な文言が重要視される背景があります。
コーヒー店での体験:「察してもらう」より「伝える」
私のコーヒー店での店主さん達との関係を振り返ってみると、面白いことに気づきます。
もし日本風にしていたら:
- 店主さんが話しかけてくれるのをじっと待つ
- ありがたい気持ちは心の中にしまっておく
- 「お忙しい中、すみません」と遠慮しまくり
実際に私が試みたアメリカ風のアプローチ:
- 自分から「どこから来たんですか?」って聞いてみる
- 毎回ちょっとしたチップで感謝を「形」にする
- 「今日は忙しそうですね、がんばって!」って素直に声をかける
その結果、私たちは「お店の人とお客さん」から「知り合い」になって、最終的には50杯のコーヒーを特別に提供してくれるまでの信頼関係になることができました。

日本人がアメリカ的環境で気をつけるといいこと
1. 思っていることをちゃんと言葉にする
日本風: 「ちょっと難しいかもしれません」(実は反対)
アメリカ風: 「この提案には反対です。理由は…」
ㅤ
私がコーヒー店で店主との関係を築いた時も同じでした。最初は日本的に「お忙しい中すみません」と遠慮がちに接していたのですが、思い切って「どこの出身ですか?」とストレートに聞いてみたことで関係が一気に深まりました。相手に察してもらうのを期待するのではなく、自分の興味や意見をはっきり表現することで、より深いコミュニケーションが生まれるのです。
ㅤ
ローコンテクスト文化では、遠回しな表現は時として無関心や消極性と受け取られることもあるため、積極的な意思表示が重要になります。また、議論の場では反対意見を述べることも建設的な貢献として評価されるため、恐れずに自分の立場を明確にすることが求められます。
2. 分からない時は遠慮しないで質問する
日本風: 分からなくても「分かりました」って言ってしまう
アメリカ風: 「ちょっと説明してもらえますか?」
ㅤ
理解できない時は遠慮しないで質問する方が、「ちゃんと聞いているな」「関心があるんだな」っていう良いメッセージになります。ローコンテクスト文化では、質問することは学習意欲の表れとして歓迎されます。むしろ、分からないのに質問しないことの方が、後々大きな問題を引き起こす可能性があると考えられています。私もコーヒー店で「ニューヨークにはいつから来ているのですか」、「なぜニューヨークに来たのですか」と質問したことで、さらに会話が盛り上がりました。理解できない時は遠慮しないで質問する方が、「ちゃんと聞いているな」「関心があるんだな」というポジティブなメッセージになります。
3. 「ありがとうの気持ち」を具体的に表す
日本風: 心の中で感謝
アメリカ風: ありがとうを言葉と行動ではっきり示す
私が言葉でお礼を伝えたり、チップで感謝を表したように、「ありがとう」という気持ちを相手に分かってもらえる形で伝えることが大事です。ローコンテクスト文化では、感謝の気持ちも具体的に表現されることで初めて相手に伝わると考えられています。「いつもありがとう」よりも「昨日の○○、本当に助かりました」といった具体的な感謝の方が、相手にとって意味のあるフィードバックになります。また、感謝を行動で示すことで、言葉だけでは伝わらない誠意を表現することもできます。
4. 自分の成果を素直にアピール
日本風: 謙遜して「たいしたことではないです」
アメリカ風: 「ありがとうございます。予定より早く完成させました」
ㅤ
特に欧米では謙遜は理解してもらえないことが多く、そのためにちゃんとした評価を受けられないこともあるかもしれません。ローコンテクスト文化では、自分の貢献や成果を明確に伝えることが、チームや組織にとって有益な情報共有とみなされます。謙遜は時として自信のなさや能力不足と誤解される可能性があるため、事実に基づいた適切な自己評価を伝えることが重要です。成果を共有することで、他のメンバーも学びを得ることができ、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。この例のように、褒められた時は素直にお礼を言い、時と場合によっては「なぜそうすることができたのか」、背景を説明することも効果的です。
5. 相手への関心を素直に表現
日本風: 遠慮して距離を保つ
アメリカ風: 「髪を切ったのですね」「良い週末を!」
ㅤ
相手への関心や気遣いを素直に表現することで、ぐっと距離が縮まります。ローコンテクスト文化では、関心を示すことが人間関係構築の第一歩とされています。私がコーヒー店で「今日は工事の音がうるさくて大変ですね」と声をかけたところ、店主が嬉しそうに状況を説明してくれ、共感を通じて絆が深まりました。相手の状況に気を配り、それを言葉で表現することで、単なる取引関係を超えた人間的なつながりを築くことができます。
どうして直接表現の方が深いつながりができるの?
1. 勘違いが起こりにくい
察してもらうコミュニケーションだと、相手が理解できなかったり、間違って受け取ったりする可能性があります。でも、ストレートに話すと、お互いの気持ちを正確に伝え合うことができます。ㅤ
ローコンテクスト文化では、誤解を避けることが効率的な関係構築の基本とされています。曖昧な表現による誤解は、時間の無駄だけでなく、信頼関係の悪化にもつながる可能性があるため、最初から明確に伝えることが重視されます。特にビジネスの場面では、一つの誤解が大きな損失を招くこともあるため、確実性を重視したコミュニケーションが求められます。
2. 相手が「特別扱いされている」と感じやすい
「あなたに興味があります」「あなたを大切に思ってます」ということがはっきり伝わるので、相手は特別扱いされている、と感じやすくなります。ローコンテクスト文化では、関心や好意も言葉や行動で明確に示されることで初めて相手に伝わります。私がコーヒー店で店主の出身地について質問し、ニューヨークに来た経緯の話で盛り上がったように、具体的な関心を示すことで相手は「この人は私に興味を持ってくれている」と感じることができます。このように直接的な関心を示すことは表示は、相手にとって記憶に残る特別な体験となり、長期的な関係構築の基盤となります。
3. 短時間で信頼関係が作れる
まわりくどい言い方よりも、素直なコミュニケーションの方が、短い時間で深い理解と信頼を築くことができます。ローコンテクスト文化では効率性が重視されるため、迅速な関係構築が可能です。お互いの意図や期待を早い段階で明確にすることで、無駄な探り合いを避け、実質的な関係発展に集中することができます。
さらに、ストレートな会話を通じて相手の考えや価値観をより深く理解できるため、表面的な付き合いではなく、お互いの人格や価値観を理解した上での深い関係を築くことが可能になります。私とモンゴル出身の店主も、出身やニューヨークに来た経緯などを質問する会話をした時から、より深い信頼関係が生まれたような気がします。
日本でも使える「直接的なコミュニケーション」のコツ
職場で
今まで: 「お疲れ様です」
これから: 「昨日の資料作成、お疲れ様でした。グラフがすごく分かりやすくて助かりました!おかげでプレゼンがうまくいきました」
友達同士で
今まで: 心の中で感謝
これから: 「この前はアドバイスありがとう。おかげで悩みが解決できました。あなたの言葉にすごく救われました」
家族で
今まで: 察してもらうことを期待
これから: 「今日は疲れてるから、少し休ませてもらえる?30分したら手伝うから」
両方の文化の良いとこ取りをしよう
日本人である私たちは「察する文化」で育ちながら、「はっきり言う文化」も理解できる、とても貴重な存在だと思います。この両方の良さを活かして、もっと豊かな人間関係を築けるはずです。
日本の「察する文化」の良いところ:
- 細やかな気遣いができる
- 相手の気持ちを読み取るのが上手
- みんなで仲良くしようとする姿勢
アメリカの「はっきり言う文化」の良いところ:
- 分かりやすくて効率的
- 勘違いが起こりにくい
- いろんな人と関係を作りやすい
今日から始められる3つのこと
その1:ありがとうを具体的に伝えてみる
今週、誰か一人に対して、具体的な感謝の気持ちを言葉で伝えてみてください。
ㅤ
「いつもありがとう」ではなく、「昨日○○してくれて、本当に助かりました。おかげで△△できました」という感じで。
その2:質問することを恐がらない
分からないことや気になることを、思い切って質問してみましょう。「忙しそうだから…」と遠慮しないで、「お時間のある時に教えてもらえますか?」と素直に聞いてみましょう。
その3:関心を言葉にしてみる
「お疲れ様です」の後に、相手の具体的な状況や頑張りに触れる一言を加えてみてください。
まとめ:もっと深いつながりのために
文化の違いを知ることで、私たちはもっと効果的なコミュニケーションを選べるようになります。
ㅤㅤ
「察してもらう」のを期待するのではなく、自分の気持ちや考えを言葉で表現してみる。相手への関心や感謝を、ちゃんと伝わる形で示してみる。
ㅤ
こんな小さな変化が、あなたの人間関係を大きく変えてくれるかもしれません。
ㅤ
私がニューヨークのコーヒー店で学んだのは、「言葉で表現することのパワー」でした。これは決して、日本の察する文化がダメだという話ではありません。むしろ、両方の良さを活かして、もっと豊かな人間関係を築くための新しい道具を手に入れることなのです。
ㅤ
今日から、あなたも「直接言葉で表現する」効果を試してみませんか?きっと、思っている以上に深いつながりが待っているはずです!

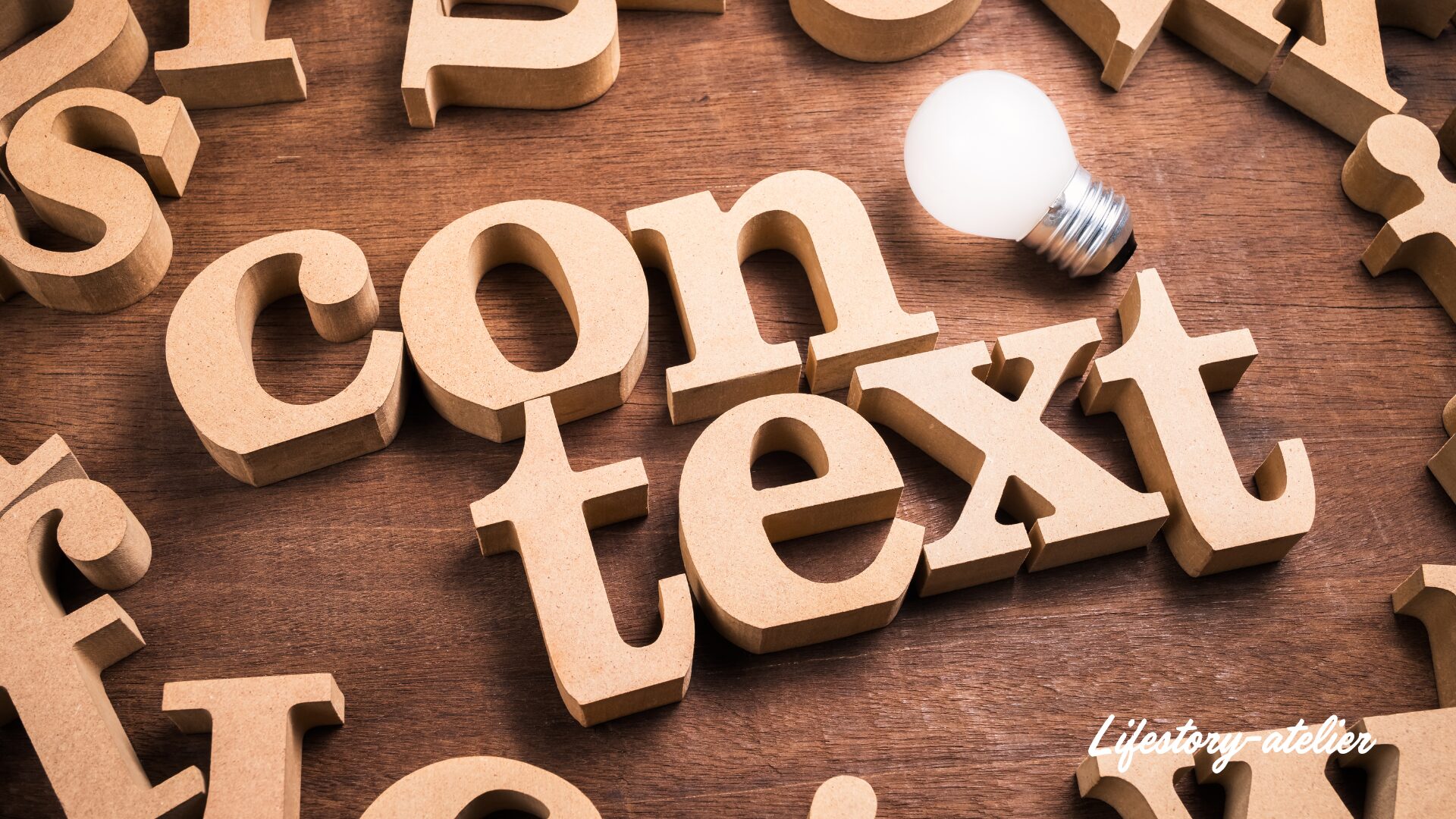
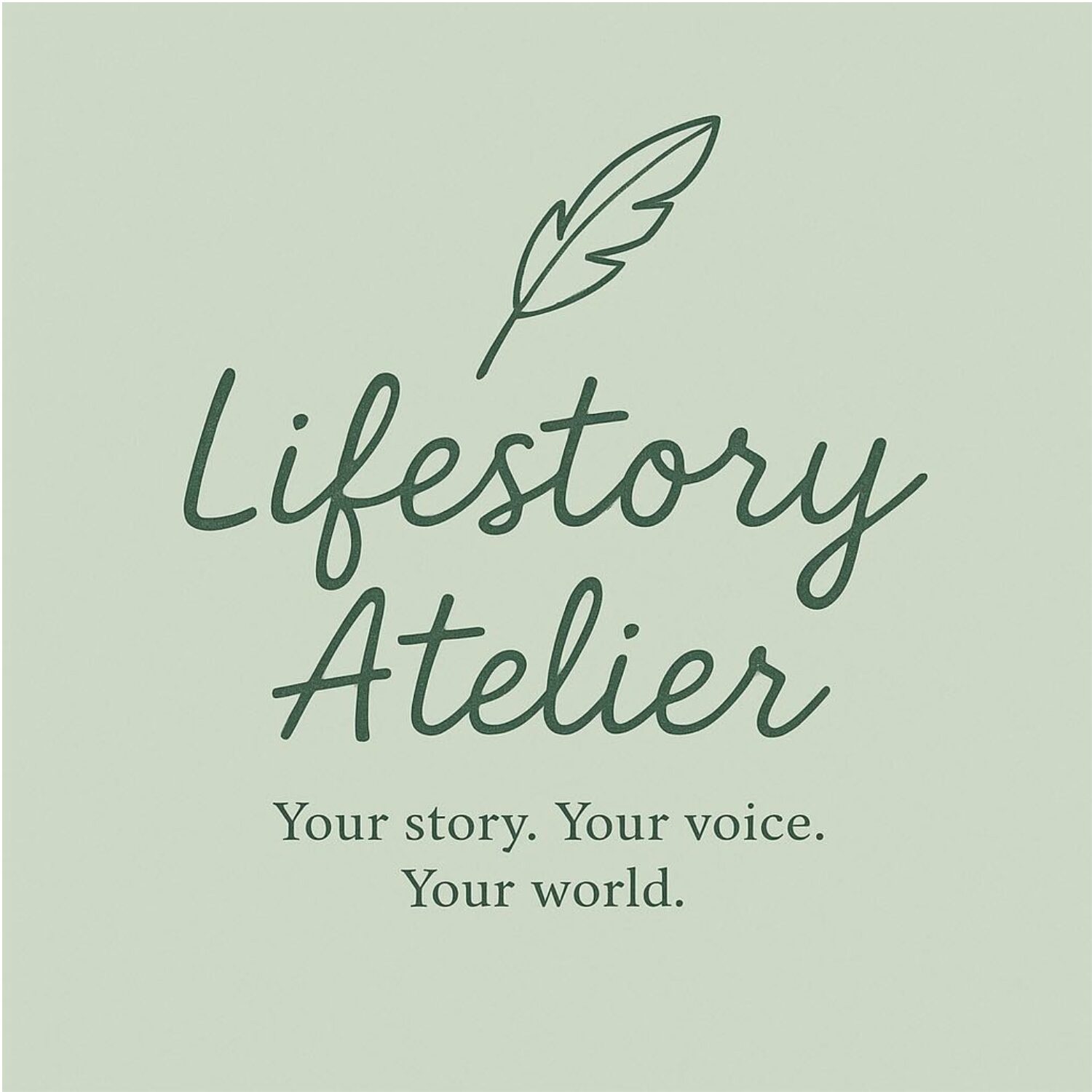





コメント